婦人科 【 子宮体がん 】
子宮体がんとは
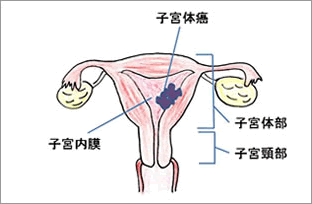 子宮は妊娠した時に胎児を育てる部分と分娩の時に産道の一部となる部分に分けることができ、それぞれを子宮体部、子宮頸部といいます。子宮体部に発生するがんが子宮体がんで、最近我が国の成人女性に増えてきているがんのひとつです。そのほとんどは、子宮体部の内側にあり卵巣から分泌される卵胞ホルモンの作用をうけて月経をおこす子宮内膜という組織から発生し、子宮内膜がんとも呼ばれています。
子宮は妊娠した時に胎児を育てる部分と分娩の時に産道の一部となる部分に分けることができ、それぞれを子宮体部、子宮頸部といいます。子宮体部に発生するがんが子宮体がんで、最近我が国の成人女性に増えてきているがんのひとつです。そのほとんどは、子宮体部の内側にあり卵巣から分泌される卵胞ホルモンの作用をうけて月経をおこす子宮内膜という組織から発生し、子宮内膜がんとも呼ばれています。
子宮体がんになりやすい人は? どのように発生するか?
子宮体がんの発生には、卵胞ホルモン(エストロゲン)という女性ホルモンが深く関わっています。卵胞ホルモンには子宮内膜の発育を促す作用があり、卵胞ホルモンが相対的に過剰である方は、子宮内膜増殖症という前段階を経て子宮体癌(子宮内膜がん)が発生するリスクが高まります。出産したことがない未経産婦、閉経の遅い女性、肥満、月経不順(無排卵性月経周期)や多嚢胞性卵巣症候群の女性、卵胞ホルモン製剤だけのホルモン療法を受けている方などが、子宮体がんになりやすいといわれています。
一方、このような卵胞ホルモンの刺激と関連なく生じるものもあります。このようなタイプの子宮体がんは、がん関連遺伝子の異常に伴って発生するとされ、比較的高齢者に多くみられます。そのほかにも高血圧、糖尿病、近親者に乳がん・大腸がんを患った方がいることなども危険因子として知られています。
主な症状
一番多い自覚症状は不正出血です。子宮頸がんに比べ、子宮体がんになる年代は比較的高齢(50歳代がピーク)ですから、閉経後あるいは更年期での不正出血がある時には特に注意が必要です。閉経前であっても、月経不順、乳がんを患ったことがあるなどということがあればやはり注意が必要です。
検査法は
子宮頸がんの検診と同様に、子宮内膜の検査も外来で十分に可能です。直接、子宮の内部に細い棒状の器具を挿入して細胞を採取して検査する子宮内膜細胞診が一般的です。疑わしいところがあれば、さらにさじ状の器具を使って組織を採取して精密検査を行い診断します。ただ、子宮体がんの患者さんは比較的高齢の方が多いので、子宮の中まで器具を挿入することが難しい方もいらっしゃいます。このような方には超音波検査で子宮内膜の厚さを測って判断することも行われます。子宮体がんになると子宮内膜の厚みが増してくることが多いので、超音波検査は有用な検査のひとつですが、初期のがんを検出できない可能性があります。
内膜細胞診および組織診断で子宮体がんと確定したら、進行期を決定するために、MRI、CT、PET/CTなどの画像検査をおこない、病気の広がり具合や、転移の有無を検査して、最終的な治療法を決定します。
治療方法
治療の主体は手術です。病気の進み具合にもよりますが基本的には子宮、卵巣・卵管、リンパ節を摘出するのが一般的です。手術により再発危険因子がみつかったり、あるいは診断した時点で手術による病巣の完全摘出が困難な場合には、手術後に抗癌剤による化学療法(通常はパクリタキセルとカルボプラチンという2剤の薬を併用したTC療法3-6コースをおこないます)や放射線治療などが行われます。若年婦人で子宮を温存し妊孕能を維持して治療することを希望される方には、ホルモン剤(高用量の黄体ホルモン剤の内服)を使って治療することも可能です。ただし、ホルモン治療の適応となるのは、前がん状態の子宮内膜異型増殖症またはごく初期の子宮体がんで、しかも一部のタイプのものに限られるので注意が必要です。またホルモン療法は血栓症などの副作用があることや再発率がかなり高いことを十分に知った上で、選択するかどうかを判断することになります。
なお、2013年の当科における子宮体がんの治療実績は22例で、全例に手術を実施しました。通常の子宮内膜がんに加えて、子宮肉腫や癌肉腫の治療も積極的に行っております。
最後に
子宮体がん(子宮内膜がん)は決して治りにくい癌ではありません。日本産科婦人科学会腫瘍委員会報告によると、全国で2005年に初回治療を受けた子宮体がんの患者さんの5年生存率は、ステージIで95.1%、ステージIIで89.2%、ステージIII で76.8%、ステージIVで23.1%でした。つまり、病気が子宮にとどまっている範囲(ステージII以下)で治療すれば、髙い生存率が期待できる疾患なのです。しかしながら、医学がどんなに進歩しても、癌を克服するには早期発見・早期治療が重要なのは変わりありません。心配な症状があれば、婦人科での検診を躊躇することなく受けることが大切です。
