婦人科 【 子宮頸がん 】
子宮頸がんとは
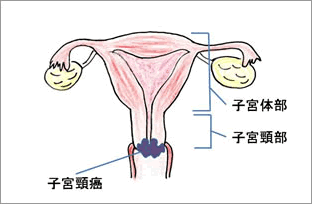 子宮頸がんは40歳代に発生数のピークがありますが、最近では特に20歳代から30歳代に増加しており、乳がんと並んで、若い女性に多いがんです。
子宮頸がんは40歳代に発生数のピークがありますが、最近では特に20歳代から30歳代に増加しており、乳がんと並んで、若い女性に多いがんです。
子宮頸がんは、子宮の入り口の子宮頸部とよばれる部分から発生します。子宮の入り口付近に発生することが多いので、普通の婦人科の診察で観察や検査がしやすいため、発見されやすいがんです。また、早期に発見すれば比較的治療しやすく予後のよいがんですが、進行すると治療が難しいことから、早期発見が極めて重要といえます。
子宮頸がんは、どのように発生するか
子宮頸がんの発生には、その多くにヒトパピローマウイルス(HPV:Human Papillomavirus)の感染が関連しています。HPVは、性交渉で感染することが知られているウイルスです。子宮頸がんの患者さんの90%以上からHPVが検出されることが知られています。HPV感染そのものは健康な女性においてもふつうにあることですが、感染しても、多くの場合、数年以内に約90%はHPVが排除されると考えられています。HPVが排除されず感染が持続すると、一部に前がん病変(異形成)が発生し、さらに数年以上かけて一部が子宮頸がんへと進展すると考えられています。また喫煙も、子宮頸がんの危険因子であることがわかっています。
子宮頸がん検診
子宮頸がん検診は非常に有効で、進行がんを防ぎ死亡を減らす効果が証明されています。多くの先進国ではほぼ例外なく、子宮頸部細胞診による検診が行われています。欧米での受診率は高く、OECDのデータによると、子宮がん検診受診率は米国が85%であるのに対し、日本は37.7%とはるかに低率であります(OECD Health Data2013)。最近ではクーポンなどの行政のキャンペーンにより検診受診率がやや上昇しましたが、全国平均で30-40%程度で頭打ちとなっており、とくに若い女性の受診率は低いままです。我が国では20歳以上の女性では、2年に1回、細胞診による子宮頸がん検診の受診が推奨されています。
子宮頸がん予防ワクチン
子宮頸がんの原因はHPVというウイルス感染ですが、子宮頸がんの60-70%の原因となるHPV16型・18型に対するワクチンが開発され、2007年頃から、世界各国で10-12歳を対象とした公費接種プログラムとしてのワクチン接種がはじまりました。このワクチンにより未感染者のHPV感染はほぼ100%予防でき、前がん病変の発生を減少させることが証明され、WHO(世界保健機構)はその有効性と安全性に基づき、ワクチン接種を推奨しています。日本においては2013年に定期接種化された後、接種後の様々な症状について再度検討するため、いったん積極的な推奨が中止されましたが、現在、再開に向けての診療体制作りや様々な検討が行われています。
主な症状
前がん病変や、初期の子宮頸がんでは症状はほとんどありません。進行した子宮頸がんでは、性交時出血、帯下(おりもの)の異常、不正性器出血、下腹部痛などがみられます。
検査法は
子宮頸がん検診や外来での子宮頸部の細胞診で、異形成や子宮頸がんの疑いのある判定が出た場合は、精密検査として、外来でコルポスコピーという拡大鏡を使用して、子宮頸部の病変の組織を採取し病理検査に提出します。子宮頸がんには、扁平上皮がん(全体の約70%)と腺がん(全体の約30%)の2つの組織型があります。この後に述べる放射線療法や化学療法の効果は扁平上皮がんの方が高いといわれていますが、治療の基本的な方針はどちらもかわりません。組織診断で子宮頸がんと確定したら、進行期を決定するために、MRI、CT、PET/CTなどの画像検査を行い、病気の広がり具合や、転移の有無を検査して、最終的な治療法を決定します。進行がんが疑われる場合は、膀胱鏡や直腸の検査をすることもあります。
子宮頸がんの治療
子宮頸がんの治療方法は、手術療法、放射線療法、化学療法(抗がん剤)の3つを単独、もしくは組み合わせて行います。
異形成や上皮内がんと診断され、今後、妊娠・出産の希望がある場合には子宮を残す治療として、子宮頸部のレーザー治療や子宮頸部を部分的に切除する円錐切除術を行います。 子宮を残す希望のない場合や、がんの浸潤が浅い場合(進行期1A1期まで)は、子宮の摘出手術(単純子宮全摘術)が行われます。がんがもう少し進んだ場合(進行期1A2期-1B-2B期まで)には、子宮に加えて腟の一部、周辺組織、靭帯(じんたい)、リンパ節を広範囲にわたって摘出します(広汎子宮全摘術)。卵巣も摘出することがありますが、リスクの少ない症例では卵巣を温存しています。腫瘍径の大きな局所進行例も術前化学療法(NAC)を行い、積極的に手術の対象としています。当科では、2010年以後安全かつ高度な広汎子宮全摘術の術式を改良・確立し、術後に起こり得る長期の排尿障害や下肢リンパ浮腫などの後遺症は、ほどんど認めなくなりました。また、婦人科がんの手術では、術後の血栓塞栓症の防止にも積極的に取り組んでおり、術後1日目から血栓予防の投薬を行っております。子宮頸がん手術後の病理検査でリンパ節転移などの再発リスクが高いと判断される場合には、再発を減らすために、術後に抗癌剤(TC療法:パクリタキセルとカルボプラチン)による化学療法を主体とした追加治療をおこないますが、時として放射線療法を追加することもあります。
がんが既に、骨盤壁や他の臓器にまで及んでいる場合(3期から4期)は、放射線療法や、抗がん剤と放射線を同時併用した治療を行います。抗癌剤はシスプラチンというお薬を週1回または3週間に1回投与することが多いです。
一方、進行期にかかわらず、年齢や基礎疾患、全身状態を考慮した上で、手術をせず、同時化学放射線療法または放射線治療のみを行うこともあります。
当院では2013年度から、放射線治療に最新のIMRT(高度変調放射線治療)である『トモセラピー』の機器が導入されました。同装置により、精度の高い放射線治療が可能になり、下痢・下血や腸炎などの消化管への副作用も劇的に減少しております。
2013年の当科における子宮頸がんの治療実績は、上皮内がんが26例、浸潤癌が24例でした。上皮内がんは全例、浸潤がんは14例に手術を実施しました。当科における過去13年間(2001-2013年)の子宮頸がん症例の解析によると、5年生存率は扁平上皮がんが全体で79.4%、腺がんが82.0%でした。進行期IBからIIB期の広汎あるいは準広汎子宮全摘術施行症例に限ると、5年生存率は扁平上皮癌が81.8%、腺癌が91.8%でした。日本産科婦人科学会腫瘍委員会報告による全国統計(2005年治療開始症例)と比較すると、扁平上皮癌ではほぼ同等(全国平均80.4%)、腺癌では当院がやや良好な生存率(全国平均75.7%)という結果でした。
最後に
子宮頸がんはごく初期のがんであるならば、子宮を残すことが可能であり、レーザー治療や円錐切除などで治療が可能です。
浸潤がんの場合でも、I -II 期の早期であれば比較的治療成績の良いがんです。子宮頸がん検診で早期発見することが可能であり、早期治療が重要です。
