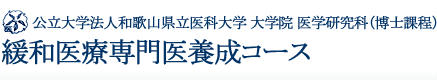| ホスピスと緩和医療 |
 大阪大学大学院 医学系研究科 緩和医療学 教授 恒藤 暁 |
| 緩和医療のルーツはホスピスといわれるものです。ホスピスは、中世西部ヨーロッパで生まれたもので、旅行が今ほど安全ではない当時の巡礼者をもてなす所として生まれたとされています。 1967年、イギリスにセントクリストファー・ホスピスができ、医者や法律家、聖職者などのチームが協力してケアに携わることが始まったことが、近代的なホスピスのはじまりとされています。 |
わが国では1981年に聖隷三方原病院で最初のホスピスができ、演者が以前に勤めていた淀川キリスト教病院に1984年にできた緩和ケア病棟は2つ目です。
1990年、診療報酬項目として「緩和ケア病棟入院料」が新設され、一定の条件を満たす緩和ケア病棟への入院に対し、定額制の医療保険が適用されるようになりました。経済基盤ができたおかげで、現在約180の緩和ケア病棟が国内にあります。ただし、イギリス並みの施設が必要なら、人口比率から考えると400近い数が必要になり、まだ、絶対数が少ないといえると思います。
近代ホスピスの母、セントクリストファー・ホスピスのソンダース博士は、トータルペインという概念を提唱しています。英語のペインという言葉は意味が広く、単に身体的苦痛と捉えるのではなく、精神的苦痛、社会的苦痛、そしてスピリチュアルな苦痛も含みます。患者さんのトータルペインに対し、トータルケアを提供するのがホスピスであり緩和ケアであるといえます。
また、2002年にWHOが緩和ケアの定義を変更しています。変更点の1つは、がん緩和ケアに限定せず、がん以外にももっと広く適用すべきと提唱・提案しています。2つ目は、家族のケア、家族のQOLも考慮する点です。QOLのLつまりライフには、生命、生活、人生、生きがいといった意味を含み、患者と家族の両方のライフの質を、いかに改善するかということが、緩和ケアの課題になると思います。
緩和ケアの目標について、5つの点についてお話しさせていただきます。
トータルケアともいえ、4種類の苦痛に対するケアです。
1.身体的苦痛
淀川キリスト教病院ホスピスでの調査によると、身体的苦痛として最も多い症状は全身倦怠感、次に食欲不振、そして3番目が痛みでした。他にも、便秘、不眠、吐き気などがあり、こうした症状は亡くなる1カ月前ごろから増える傾向があります。したがって、亡くなる1〜2カ月前に入院しているのが現状ではないかと思われます。
また、日常生活動作に関する調査では、亡くなる2週間前で2割、1週間前で半数が自力でトイレに行けなくなっていました。
これらのことから、最後の1カ月を家で過ごそうとすると、先述の身体的苦痛をしっかりとマネジメントしてくれる医師・医療従事者が必要で、最後の数週間は介護をしてくれる家族や介護者が必要になります。寝たきりになって介護が不十分だと、床ずれによる痛みが生じます。
2.精神的苦痛
精神的苦痛の中には、不安・いらだち、せん妄・不穏、抑うつ、認知症などがあります。ホスピスに入院している患者さんでも、精神的な苦痛が無く穏やかに過すごせる患者さんは4割という現実があります。
病状や悪いことを知らされていなければ、不安も感じず落ち着いていられるかもしれません。しかし、生きていくということには多少の不安が伴うもので、不安に対して工夫・努力することがより人間的であると考えれば、悪いことを一切遮断することが適切かどうか考えていく必要があると思います。
3.社会的苦痛
人は社会的に存在するので、経済上・生活上・職業上の問題、社会復帰、遺産相続など、社会的な問題で悩む方もいます。
4.スピリチュアルペイン
スピリチュアルペインを分かりやすく訳すとすれば、危機的な状況における“生きる意味と価値の問いかけ”といえると思います。「なぜ私が?」(不公平感)、「そんなことをしても意味がない」(絶望感)など、様々な人間の根源に係わる悩みがあらわれるとされます。今までの医学教育と医師は避けてきましたが、緩和ケアでは、スピリチュアルペインに正面から向き合っていくということが期待されます。
理想と現実の差を縮めていくことがQOLの向上につながるといえます。良くない現実をより良い方向に改善していけるとは限らないため、逆に、期待の方を現実に近づけていく作業も必要になります。これには、患者さんとのしっかりとした人間関係を築きながら、良くない現実を受け止めていただけるようなコミュニケーション、アプローチが必要となると思います。
ここでもまた、悪いことを伝えないことがはたして本当に良いのだろうかということになりますが、適切なコミュニケーションにより伝えていくことが、QOLの向上に繋がるのではないかと思います。
コミュニケーションについては、シンプソンという人の面白い例えがあります。「真実と薬。真実は薬のようなものである。つまり真実には薬理作用がある。真実の投与量が不十分であると効果が十分に得られず、治療者への信頼を損ねる。逆に投与量が多すぎると異常反応や副作用が出現する。」と。
いかに医療従事者、ご家族が、悪い知らせを患者さん本人と分かち合えるかどうかが、患者さんのQOLや最後の時間の過ごし方に影響することを、医療従事者は肝に銘じて対応する必要があると思います。今の医療現場では、患者が望んでいても伝えず、楽観的な良いことしか伝えないことが起きているからです。
心のケア、精神的援助については、どうしたら良いのか、よく質問を受けます。アメリカのカウンセリング学会会長だったベルは、「Caring+Confrontation=Growth」と表現しています。このケアという言葉は、人との人間関係を築くための傾聴、受容、共感といえます。コンフロンテーションは、人としっかりと向き合う、つまり対峙することで、人間関係における相互検討、自己吟味、自己洞察を意味します。したがって、いかに傾聴し、受容し、共感していくか、そしてその後で慎み深く問いかけることが重要であると思います。
現代の医療は一人ですべてを行うことは不可能で、すべての医療にチーム医療が必要といえますが、なかなかうまく機能しない現実があります。
その理由には、医師の非協力、チームメンバーの力量不足、コーディネーターの不在などが挙げられます。
チーム医療の長所には、総合的な判断が可能になる、多くの必要を満たせる、方針が一致した医療が可能、パターナリズム(父権主義)から脱却できる、互いに理解し、援助し合えるといったことがあります。
医療現場で大切なのは、医療従事者と患者さん、ご家族の関係だけでなく、医療従事者どうしもより良い人間関係を築けるかということに尽きると思います。
シームレスケアのシームは縫い目を意味し、継続ケアという意味です。家で過ごせるときは家で過ごし、家で過ごしにくくなったら入院し、落ち着いたら家に帰るといった感じで、家と病院と行ったり来たりすることを続けることが今、重要であるといわれています。これには24時間対応できる医療機関が必要ですが、現実には医療崩壊といわれる状況にあり、今後、整備していく必要があると思います。
家族の問題としては、看病疲れ、患者さんを取り巻く人間関係の悩み、経済的な問題、そして、気持ちの葛藤があります。家族として一日でも長生きして欲しいという思いと、十分に苦しんだし戦ってこられたので、早く楽にしてあげたい、自分も楽になりたい、そういう相矛盾する様々な苦しみ・悩み・葛藤があるということを理解していただければと思います。
患者さんが経験していることは、医療従事者は経験していないことであり、緩和医療においては患者さんから教わる、学ぶことが重要であるように思います。
すべての医療従事者が緩和ケアの知識と技術を身につけ、どこでも誰でも行えるようになることで、シームレスケアが行える医療体制を構築され、専門的な緩和ケア病棟が要らなくなるのが理想であるかもしれません。
2008年4月に施行された、がん対策基本法のキーワードとして、均てん化というのがうたわれています。これは、どこでもだれでも等しい診断と治療、また緩和ケアを受けられるように整備していくことです。
この均てん化のために、化学療法、放射線治療、緩和医療の専門医を育成が必要となり、このがんプロフェッショナル養成プランがあるわけです。
また、がん対策基本法の付帯決議として、緩和ケアについては、がん患者のQOLを確保するため、専門的な知識および技術を有する医療従事者の育成に努め、医療・緩和ケアを受けられる体制の整備を進めるとされています。
緩和医療教育が、がんプロフェッショナル養成プランの進行とともに、整備され、充実していくことが期待されています。