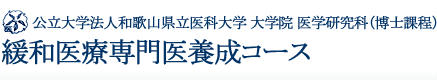| ケアとキュア |  和歌山県立医科大学 麻酔科学教室 教授 畑埜 義雄 |
| 外科的な治療は「キュア」で、苦痛の除去は「ケア」です。戦後、医学教育は診断・治療学を中心に、日本の医学を発展させました。しかし、今の日本の医療は、医学教育もすべて、放射線、内科的治療、先端医療、特定機能治療、もう全部治療が中心で、ケアの概念が乏しく、教育にすらケアという言葉がまったく出てこないのが実状です。治療が“縁の上”とすると、ケアは“縁の下”になってしまいます。本来、医療には縁の下の部分はないはずなんですけれど、日本独特の文化ができてしまったように思います。精神的苦痛に対しては精神科医や臨床心理士が、社会的苦痛に対してはソーシャルワーカーがそれぞれ対応します。ところが、このスピリチュアルケアを誰がどのように行うかということが、問題になってきているわけです。 |
低いモルヒネ使用量
ケアに対する世界の取り組みを考えるとき、がん医療を指標とすれば良いのではないかと考えています。末期がんでは、がん患者の80〜90%の方が、痛みを持つようになります。この痛みに対し、WHOが1986年、がん性疼痛からの解放の指針を発表し、安価なモルヒネをうまく使うことで、がん性疼痛の除去ができることを世界に示したわけです。しかし、日本の1人あたりのモルヒネ使用量は、最も進んだカナダ・オーストリアの9分の1にも届きません。すると、日本の方が痛がっている患者さんが多いのではないかと考えるわけです。これは、痛みを除去しようとするケアという文化が根付いていないあらわれといえると思います。
緩和ケアというのは治癒、治そうということを目的とした医療に感応しなくなった患者に対して行われる、「積極的で、全体的な医学的ケア」と定義しています。
エレファントマン
「エレファントマン」という映画をご存じか思います。これは、19世紀末のイギリスの実話を元にしています。頭蓋の形成異常をきたして徐々に肥大してきた少年が、見世物として扱われていたのを、王立ロンドン病院の外科医が、生涯病院で暮らせるようにしてあげるんです。映画の中で、少年が「ここでキュア、治せるか」と尋ねます。その時に外科医はこう答えます、「キュア(治療)はできないが、ケアはできる」と。19世紀のイギリスの医師に、キュアとケアの概念が根付いていることを物語るエピソードだと思います。
医療には、このようなキュアとケアのバランスが必要だと思いますが、現在は教育方法によるのか、ケアの比重が非常に低い時代といえます。
日本のホスピスの歴史と和歌山県立医大の取り組み
医療におけるキュアとケアのバランスの必要性を、学生に教え、そして患者さんにも教えようと考え、ケア文化創生のため、和歌山県立医大で「ケアマインド教育」ということを始めました。具体的にはまず、緩和ケア病棟を作ること、もう一つは、学生の医療問題ロールプレイングによる疑似体験です。
緩和ケア実習では非常に、学生達が感性を養ってくれているように思います。また、医療問題ロールプレイングでは、シナリオ・監督・カメラなどすべて学生自身でやり、20〜25分の寸劇を作る中で、研修医や学生にケアマインドを導入しようと取り組んでいます。
このような教育を通じて、研修医や学生にケアマインドを導入しようとしています。ケアについての意識を持った人材が生まれて、現在や将来の医療を担ってくれると思っています。
がんによる苦痛とケア
がんの4つの苦痛というのが知られています。痛みや全身倦怠などの身体的苦痛。死ぬことの不安、孤立感やいら立つ精神的苦痛。経済的な問題、子供の教育、遺産問題などの社会的苦痛があります。
それに、生きる意味とでもいいますか、スピリチュアルな苦痛があります。これらの4つの苦痛が相互に働き、いわゆる全人的苦痛、トータルペインとなると捉えています。
身体的苦痛に対する対応は、医師や医学療法士、看護師、薬剤師が担います。精神的苦痛に対しては精神科医や臨床心理士が、社会的苦痛に対してはソーシャルワーカーがそれぞれ対応します。ところが、このスピリチュアルケアを誰がどのように行うかということが、問題になってきているわけです。
治療中心主義とスピリチュアルケア
スピリチュアルケアを誰が解決するか、これは新たな医療ケアに属すると感じますが、どのようにして良いかわからないというのが、現実だと思います。
死後や死者をどう捉えるのか。生きることとは何か、死ぬこととは何か。こうしたことが死生観なんですが、受けた教育、職業、過去の人生の成功や失敗、信念などが関係します。そして、宗教・思想というものが一番大きいかもしれません。
スピリチュアルペイン、すなわち精神的な・霊的な苦痛とは、人生の意味、目的を喪失すること、自己や人生に対する不確実性の増大といったものです。また、後悔、罪の意識といったものがたくさんあらわれます。
例えば、キリスト教でしたら、チャペルとかで対応できるものだと思いますし、キリスト教では、生、死、そして復活、そして永遠の命を得るといったプロセスがあるようです。また、インドでしたら、日常の延長線上に火葬場が存在しており、常に死に面している。で、死はすべての終わりではなく、転生する道筋にすぎない、というようにネットでは書いてあります。
日本人の死生観とスピリチュアルケア
日本の宗教や思想は、儒教・道教や様々な思想哲学が混在していて、そこから、諸外国と違いが生じてくると思います。死が身近になくなった現在では、死とは、経験的に知り得ない恐怖になります。肉体がなくなっても、霊魂が残るというところに拠り所を求めて、恐怖がある程度和らいで、悲しみになるのではないかと。これが、日本的ではないかと思います。多様化した死生観を持った日本人に対して、どのような形でトータルケアができるんだろうかというと、やはり宗教者だけでなくて、哲学者、社会学者、医療者、心理学者などが、スピリチュアルケアに入ってくる必要がなかろうかというのが、演者の考えです。
そして、スピリチュアルケアに対して医療者ができることは、理解的態度をとり、共感すること、これがトータルケアにつながっていくと思います。