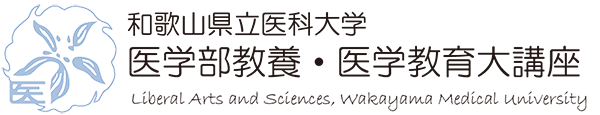夏の公開講座 2018
講演概要
1日目 8月4日(土曜日)
13:00 英詩を読もう英語教室 廣田麻子
13:00 英詩を読もう
英語教室 廣田麻子
みなさんとご一緒に読むシェイクスピアは、劇作家として有名ですが、詩人でもありました。『ソネット集』という恋愛詩集を書いています。とくに彼は比喩の名人でありました。比喩というのは、女性を花にたとえるように、物事の説明に、これと類似したものを借りて表現する修辞のことです。比喩などというと、小難しくて面倒だな、と思われるでしょうか。現在なら、愛する人の美しさを愛でたいと思えば、写真を撮ることができます。写真の中の美しさはいつまでも保存できます。携帯電話の待ち受け画面にでもしておけば、その美しさにいつでも触れることができます。また、動画を撮ることもできます。動画であれば、まるで生きているかのように、動きや表情まで保存できます。でも、そのような手段のなかった16世紀と17世紀の境目の頃を想像してみましょう。「時」が愛する人の美しさを奪おうと迫り来るなか、シェイクスピアはその美しさを言葉に残そうとしたのです。「時」の力は強大で、生きとし生けるものすべてを死へと追いやることができます。その「時」に対して、シェイクスピアは言葉でもって立ち向かいました。18番のソネットではシェイクスピアは愛する人を「夏の日」にたとえています。シェイクスピアの言葉が「時」に勝るかどうか、読んでみましょう。
14:45 京大における原子核物理学研究の源泉 ~荒勝研究室の時代~物理学教室 牧野誠司
14:45 京大における原子核物理学研究の源泉 ~荒勝研究室の時代~
物理学教室 牧野誠司
京大における原子核物理学研究の源泉を、荒勝文策の足跡を中心に辿ります。荒勝グループは、加速器等を用いた原子核反応、特に核分裂反応の実験を行い、それは太平洋戦争中も続きました。荒勝グループの研究については、資料の多くが行方不明でしたが、近年、GHQによって没収された荒勝グループの実験ノートの一部がアメリカ合衆国議会図書館で発見され、アメリカ合衆国公文書館で機密指定解除となった資料、荒勝グループメンバーのご遺族から公表されたメモ等と合わせて、明らかになりつつあります。荒勝グループによる広島原爆調査、戦後のGHQによるサイクロトロン廃棄などの話とともに、科学と戦争・軍との関係について考えたいと思います。
2日目 8月5日(日曜日)
13:00 好みと価値の行動分析学心理学教室 石井 拓
13:00 好みと価値の行動分析学
心理学教室 石井 拓
「価値が高い」,「価値を高める」といった表現は日常的に見られます.では,価値の高さはどのように測ればよいのでしょうか.心理学の1つである行動分析学は,ヒトや他の動物の行動を手がかりとしてこの問題に取り組むことで,価値を測る技法を開発し,価値の法則を徐々に明らかにしてきました. 価値を測るための手がかりの1つは「選ぶ」という行動です.2つ以上のものを比べて選ばれたものは好ましい(選好される)もので,価値が高いものだと考えられます.このことを使って,ヒトを対象とした心理学では行動分析学が成立する以前から,一対比較法という技法で好ましさを尺度(ものさし)の上に位置づけてきました.しかし,一対比較法は実施するための制約が大きく,選好や価値の詳しい法則を調べるには適していないこともあり,他の方法も開発されてきました.それは,行動分析学で開発された動物実験法のうち,並立スケジュールや並立連鎖スケジュールと呼ばれる方法です.この方法では,複数の選択肢の間で動物が選択を繰り返していると,餌などがときどき出現します.そこで,餌の種類,1回ごとの餌の大きさ,餌の頻度などを変えて実験が行われたところ,それらが好みの強さにどのように影響するかについて数量的な法則が明らかになりました.これはマッチングの法則と呼ばれており,動物だけでなくヒトの行動にも当てはまることが知られています. しかし,選好から物事の価値を測る方法には限界があることも明らかになっています.各選択肢を選ぶ労力の大きさが等しく変化するだけでも選好の強さが影響されたり,選択肢から得られる餌などの組み合わせ方が選好に影響したり,実験環境のさらに外側の環境が選好に影響してしまったりするのです.そこで,ミクロ経済学の考え方を行動実験に応用して,餌などを得るのに必要な労力を価格と見なし,さまざまな価格の下での消費量を調べる需要曲線分析が開発されました.この需要曲線分析により,ものの価値は価格,代替財や補完財の存在,実験場面外の経済環境に影響されてどのように相対的に決まるかが明らかになっています.そしてその知見は,ヒトのガソリン消費や,薬物依存患者の消費行動の分析にも応用されています.
14:45 粘菌から見える世界生物学教室 森田 強
14:45 粘菌から見える世界
生物学教室 森田 強
皆さんは“粘菌”という生き物をご存知でしょうか? 変形菌ともよばれる粘菌の仲間は、アメーバーのように移動しながら餌を補食したかと思うと、キノコのような形態へと変化して子孫を残すとてもユニークな生き物です。古くは和歌山出身の南方熊楠が精力的に研究したことで有名ですが、最近では日本人研究者が粘菌を使って迷路を解かせる研究によりイグノーベル賞を受賞したことで注目を集めました。粘菌の仲間は真正粘菌と細胞性粘菌に大きく分けられますが、真正粘菌は様々な色や形態のものがありとてもフォトジェニックです。一方、細胞性粘菌の見た目は地味ですが、その形態は生活環の中でダイナミックに変化し、実験材料として世界中の研究施設で利用されています。この講義では、とてもユニークで魅力的なこれら粘菌の仲間をご紹介するとともに、粘菌を使った研究がどのように人の役に立っているのかを解りやすくお話し致します。