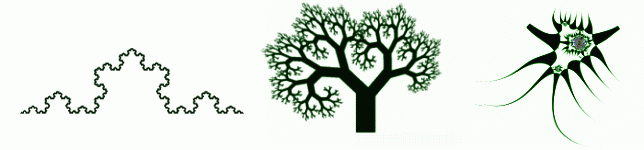和歌山県立医科大学医学部 教養・医学教育大講座
哲学・倫理学教室、医療社会科学教室、数学・統計学教室、
物理学教室、化学教室、生物学教室 主催
物理学教室、化学教室、生物学教室 主催

2013 11/2, 3
受講無料 申し込み等不要
秋の公開講座ポスター (pdf)
日時・講演題目・講師
2013年 11月2日(土)
13:30-15:00 「世代論」的に考える
医療社会科学教室 講師
本郷正武
「団塊の世代」,「全共闘世代」,「バブル世代」,「松坂世代」,最近では「ゆとり世代」など,
「○○世代」というように,ある年代の人々を分類してとらえることがあります.
どちらかといえば,「近頃の若者は……」,「あの頃はよかったのに……」というようなネガティブな使われ方をすることの方が多いかもしれません.
このように特定の世代を特徴づけ,世代間の溝を強調する「世代論」の存在に本講義では着目します.
ただし,本講義が目標とするのは,世代論のネガティブな側面を検討することや,世代間ギャップを解消することではなく,
むしろ世代論のもつ利点について紹介することです.
ある世代を切り取って分析の対象とする「ライフコース分析」という方法論があります.
ライフコース分析の先駆的著作に,エルダーの『大恐慌の子どもたち』(Elder, G.H. Jr., 1974, Children of the Great Depression: Social Change in Life Experience)があります.
いわゆる戦間期に全世界を覆った大恐慌により,アメリカでは多くの中産階級が没落していきました.
そのときに子どもだった人々は,その後どのような人生の軌跡をたどったのでしょうか.
また、大恐慌を経験していない戦後世代とはどのような違いが生じたのでしょうか.
このような,広く多くの人々に共通するような経験の有無(戦争体験、被災体験など)により,
人々の思考や人生がどのように分断され,異なる課題が生み出されているのかを考えるのがライフコース分析です.
当日はライフコース分析による研究を紹介しながら,「世代論」的に考えることの意義を考えてみたいと思います.
15:30-17:00 疑似科学を考える
物理学教室 講師
藤村寿子
2013年 11月3日(日)
13:30-15:00 生命を支えるもの
生物学教室 教授
平井秀一
15:30-17:00 フラクタルとは何か?
数学・統計学教室 講師
田中晴喜

会 場
和歌山県立医科大学
図書館棟3階 生涯研修センター 研修室
和歌山市紀三井寺811-1
和歌山県立医科大学紀三井寺キャンパス
JR紀三井寺駅西口より,徒歩約10分
和歌山バス「医大病院」または「医大病院前」下車
図書館棟3階 生涯研修センター 研修室
和歌山市紀三井寺811-1
和歌山県立医科大学紀三井寺キャンパス
JR紀三井寺駅西口より,徒歩約10分
和歌山バス「医大病院」または「医大病院前」下車
対 象
一般(高校生以上)
注意事項
- お車でお越しの方は,和歌山県立医科大学附属病院駐車場(有料)をご利用ください.
- 中学生以下の方の入場はご遠慮願います.
- 気象警報が発令されている場合は,当日の講演は中止とさせていただきます.
問合せ先
和歌山県立医科大学 総務課 Tel: 073-441-0845 Fax: 073-441-0846
e-mail: hisay@wakayama-med.ac.jp
e-mail: hisay@wakayama-med.ac.jp
過去の公開講座