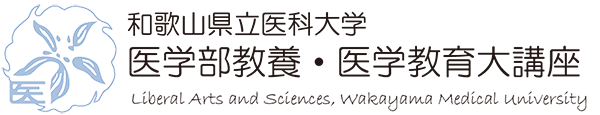夏の公開講座 2017
講演概要
1日目 8月5日(土曜日)
13:00 食の社会学 2017医療社会科学 本郷正武
13:00 食の社会学 2017
医療社会科学 本郷正武
高度経済成長以後、食品の大量生産・消費傾向は、一方でファストフードに見られる食の効率化の追求を加速させ、他方で日本古来の食文化を退廃させ、残留農薬や添加物使用による食の安全への関心を高めました。このような食に対する問題意識は、これまでにも生活クラブ生協の活動や、こんにちの有機農業や地産地消、食育、さらには「スローフード」というように言葉や形態を変えつつ引き継がれていると言ってよいでしょう。 スローフード運動は1986年に北イタリアで産声を上げ、希少作物や生産者の保護、味覚教育などの目標を掲げ、現在では150ヶ国、10万人の参加者を抱える世界的な活動となっています。日本では1993年にはじめて支部が設立されており、その中でも独自の展開を遂げている山形県の事例を本講座では紹介します。山形県では生産者のみならず、製造者や料理人、行政、映画監督などが協力することでスローフード運動が展開されているという特徴があります。当日は、このような食をめぐる連帯(あるいは分断)について考えることで、「食べること」の意味を社会学の立場から探っていきます。
14:45 おいしい料理の秘密と科学化学教室 多中良栄
14:45 おいしい料理の秘密と科学
化学教室 多中良栄
レシピどおりに作っているのになぜかいまいちおいしくならない、ということはありませんか?レシピには書かれていない料理の「コツ」を押さえていないからかもしれません。「コツ」もしっかりやっているのにやっぱりいまいち…。その「コツ」を行う理由を知らずに手順だけ追っているなら、何かをやりすぎたり足りなかったりといったこともあるかもしれません。 青菜はたくさんの水を沸騰させてさっとゆがくのはなぜでしょう?かつおだしをとる時に加熱しすぎてはいけないのはなぜでしょう?これら料理の「コツ」にはきちんとした理由があります。その理由は食品に含まれる物質の科学的な性質を知ることにより説明できます。なぜそうする必要があるのか、しないとどうなるのか、料理をおいしくする「コツ」の秘密を科学的にみていきましょう。
2日目 8月6日(日曜日)
13:00 数学の役立たせ方 ― ユークリッドの互除法を例に ―数学・統計学教室 武田好史
13:00 数学の役立たせ方
数学・統計学教室 武田好史
多くの数学者は,人々の日常生活を念頭に置きながら研究しているわけではありません.しかしそれは,数学が我々の日々の暮らしと全く関わらないとか,何の役にも立たないということを意味するものでもありません.
例えば学校教育で有名な古代ギリシアの「ユークリッドの互除法」(紀元前3世紀ごろ)は「最大公約数を求める」という純粋に数学的な動機から考え出されたものと思われますが,中国南北朝時代の数学の教科書「孫子算経」の中ではより進んだ形で(剰余定理として)述べられており,更にそれが伝わった日本では江戸時代に「百五減算」という名のある種の知的ゲームに形を変えて普及していました.
この講演では,誰もが知っていて,かつ誰も日常生活では役に立つとは思ってもいない「ユークリッドの互除法」及びそれに続く研究が,現代のIT社会では一翼どころではなく,ほぼ全てを担っている様を紹介します.
講演中止のお知らせ 8月6日(日)の英語教室廣田麻子氏による「麻酔のはなし」は中止となりました.