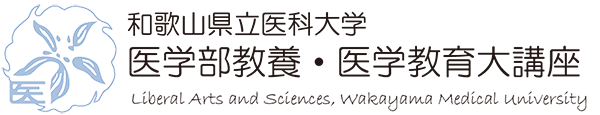夏の公開講座 2016
講演概要
1日目 8月6日(土曜日)
13:00 「頭のよさ」の心理学心理学教室 石井拓
13:00 「頭のよさ」の心理学
心理学教室 石井拓
「頭のよい人」と聞くと、計算のはやい人、記憶力の優れている人、会話の流暢な人など、私たちはさまざまな人を思い浮かべます。そもそも「頭のよさ」には何種類もあるのでしょうか。それとも、根本的な「頭のよさ」は1つなのでしょうか。人間の知能を調べる心理学研究は、100年余り前から「頭のよさ」の測り方を開発しながらこの疑問に取り組んできました。この講演ではまず、知能のあり方について現在知られている一応の定説を紹介します。また、知能の測定方法や、そこからくる問題点についても解説し、知能の重要性を過大評価、または過小評価せずに、正当に評価するにはどう考えたらよいかをお話しします。
次に、知能に対する遺伝、環境、加齢の影響についても解説します。一説によると、知能の高さの50%は遺伝によって決まると言われています。このことは、知能を高めようとする生後の努力のうち50%は無駄であるという意味なのでしょうか。また、「頭のよさ」は20代でピークに達し、それ以降は低下していくという説もありますが、それはどこまで本当なのでしょうか。講演の後半では、これらの疑問に取り組んだ研究について、データを交えながら紹介します。
最後に、頭をよくするにはどうしたらよいかについてお話しします。この問題については実証研究が始まってから日が浅いので決定的な答えを示せませんが、現時点で有力な説を紹介します。
14:45 分散と標準偏差 ― その数学的意味 ―数学・統計学教室 武田好史
14:45 分散と標準偏差 ― その数学的意味 ―
数学・統計学教室 武田好史
統計処理でまず思いつくのは平均でそれが意味するところは想像に難くありませんが,分散は何を表すものなのでしょうか.学校の授業では「分布の広がり具合を示す」と教わりますが,そもそもなぜ“二乗”で考えるのでしょうか.
歴史をたどると,分散はフランスの数学者 Adrien-Marie Legendre(1752-1833)やドイツの数学者 Johann Carl Friedrich Gauss(1777-1855)らが考案した最小二乗法に始まるといわれており,そこには数学的な理由が潜んでいます.
本講演では単純な例をもとに,広がり具合を二乗で考える数学的理由を解説していきます.
2日目 8月7日(日曜日)
13:00 毒と薬について化学教室 多中良栄
13:00 毒と薬について
化学教室 多中良栄
毒、あるいは薬に対してのイメージにはどのようなものがあるでしょうか。毒は害になる・怖いもの、薬は役に立つ・いいものといった言葉があがるかもしれません。実際、命や健康を害する毒と、病気や傷の治療に使われる薬は言葉としては全く逆の意味を持ちますが、ヒトや生物になんらかの作用を及ぼす「生理活性物質」であるという点では同じものといえます。今回は、毒や薬として作用する物質について、その構造なども含めて化学的な視点から紹介したいと思います。
14:45 性の起源生物学教室 山崎尚
14:45 性の起源
生物学教室 山崎尚
ヒトを含めたほとんどの生物には何らかの形で「性」があります。性は有性生殖するための仕組みの一つです。有性生殖は遺伝子の交換を行うことによって個体の遺伝的多様性を広げ、結果として生物を進化させる仕組みとも関係しています。この講座ではヒトの男女とは大きく異なる生物の「性」のあり方を紹介し、性の起源と性が存在する意義を考えたいと思います。