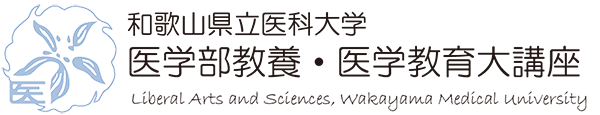夏の公開講座 2015
講演概要
1日目 8月8日(土曜日)
10:30 サリドマイドの今医療社会科学教室 本郷正武
10:30 サリドマイドの今
医療社会科学教室 本郷正武
かつて睡眠薬や鎮静剤として使用されていた「サリドマイド」という市販薬がありました(商品名は「イソミン」など)。日本では1959~1962年頃にかけて、妊娠初期のつわりの軽減のためにサリドマイドを服用した妊婦が上肢・下肢・耳の先天的奇形をもった子どもを出産するという事態が数多く起こりました。ところが、1961年にはドイツの小児科医レンツ博士がサリドマイドと奇形との関連を報告する、いわゆる「レンツ警告」があったにもかかわらず、日本では早期の回収命令・製造停止に至らず、1,000人以上の被害児が出るという大きな「薬害」問題となりました。
こうして「悪魔の薬」として闇に葬られたかに思えたサリドマイドが、日本では2008年から再承認されています。どうしてサリドマイドは再承認されるに至ったのでしょうか。本講義では、サリドマイド「薬害」を未然に防いだアメリカの事例や、サリドマイドのいわば「光」の部分について紹介しながら、「薬害」問題が産み落とした医薬品規制という今日的課題について考えてみたいと思います。
13:00 生物の歴史 ~ 生命の活動は地球をどのように変えたか生物学教室 山崎尚
13:00 生物の歴史 ~ 生命の活動は地球をどのように変えたか
生物学教室 山崎尚
生物の歴史は約40億年前に始まりました。まずは生命誕生時の地球の姿を知るために、地球がどのように誕生したか、から話を始めます。生命進化の初期段階で「鍵」となるのは、大気中の二酸化炭素濃度と酸素濃度の変化で、この変化と生命進化の深い関わりを紹介します。生命体の初期進化は海中で進みましたが、約4億年前に生命体はようやく陸地へ進出できました。なんと30億年以上の間、生命体が陸地へ上がれなかった理由を次にお話しします。これも大気の組成に関係があるのです。そして、進化の過程では何度もの大量絶滅が起こり、地球上の生命体の半数以上が絶滅したこともあります。なぜ大量絶滅が起こり、これは生命進化にどのような影響を与えたか、最後に絶滅と進化の関係を紹介します。今回、振り返る生命の歴史では、ヒトは主人公ではありませんが、ヒトのこれからを考える一助にはなる、と思っています。
14:50 ニュートリノの不思議物理学教室 牧野誠司
14:50 ニュートリノの不思議
物理学教室 牧野誠司
皆さん,掌を太陽に向けてみてください.その手を,昼夜問わず,毎秒約10兆個のニュートリノが太陽からやってきて通り抜けています(夜は地球の反対側から地球を通り抜けてやってきていることになります).痛くもかゆくもありませんね.ニュートリノは非常にまれにしか反応を起こしませんので,なかなか検出できません.したがって,ニュートリノの実験ではいろいろな工夫がなされています.ところで,ニュートリノはβ崩壊を説明するためにパウリが1930年に存在を予言し,1956年にようやく発見された素粒子です.その後,様々な実験により,ニュートリノ振動と呼ばれる現象が発見され,質量がゼロではないということがわかりました.ニュートリノの発見からの歴史をたどり,ニュートリノの他分野への応用についても紹介します.
2日目 8月9日(日曜日)
10:30 遺伝子操作の光と影生物学教室 平井秀一
10:30 遺伝子操作の光と影
生物学教室 平井秀一
遺伝子操作と聞いて何を思い浮かべるでしょう?遺伝子を意のままに繰ることにより創り出された何やら珍妙な生物、農作物の品種改良とその安全性に関する議論、それとも近年話題になったiPS細胞でしょうか。遺伝子操作により創り出されるものは実に多種多様です。ただ、今の所あまり身近に感じないという方が多いのではないでしょうか。本講座ではそもそも遺伝子操作とはどのような技術で、何の役に立つのか、そしてその利用にあたり何が危惧されるのかといったことについてお話しし、徐々に私たちの生活に浸透しつつある遺伝子操作の産物との付き合い方について考えます。
13:00 罰の効果と大きな副作用心理学教室 石井拓
13:00 罰の効果と大きな副作用
心理学教室 石井拓
しつけや教育に罰は必要か.これについて考えるとき,罰についての科学的研究からは何が言えるでしょうか.まず,学習心理学で定義されている罰と,親や教師などが罰のつもりで行っていることとの間にはズレがあり,後者は必ずしも罰として有効ではありません.次に,罰が有効であるためにはさまざまな条件が揃っている必要があり,罰をうまく使うコツは非常に難しいものです.また,それ自体は効果のある罰であっても,望ましくない副作用をもっている場合があります.さらに,罰を与えることで達成しようとしているしつけや教育は,罰を使わずに行うほうがよりよく達成できる場合がほとんどです.このような研究結果を理由として,日本行動分析学会は罰のうちでも体罰の使用に反対する声明を昨年発表しました.今回の講演では,この声明の裏づけとなっている研究や実験について分かりやすく解説するとともに,体罰などの罰を使わない教育やしつけの方法を紹介します.
14:50 日常に潜む確率の話数学・統計学教室 田中晴喜
14:50 日常に潜む確率の話
数学・統計学教室 田中晴喜
例えば,一クラスに40人の生徒がいた場合,同じ誕生日の人はいるでしょうか?また,その確率は何パーセントぐらいだと思われますか?実は,直感的に予想した答えと,実際に確率を計算したときの答えに大きな違いが出ることがあります.そのような話の1つとして3人の囚人問題,身近な問題としては,クーポン収集問題(全種類のキャラクターカードを集めるのに必要となるカードの枚数),くじ引きの原理(先手が得か後手が得か)など取り上げ,また,パスカルとフェルマーによって始まった確率論の歴史や現在の確率論に大きな貢献をしたコルモゴロフについても紹介します.