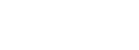若手精神科医に薦める3冊


精神科医師志望の若者に
医局長 辻富基美 講師
本を薦めるのは難しい。薦められたことで、逆にその本を読む機会を遠ざかってしまった遠くない記憶がある。もちろん、薦められたおかげで読めた本も多い。本と出会うタイミングは、人生で大切かもしれない。
精神科医として十数年の自身であるが、読書の経験値は未熟で人に自慢できるものではない。下に列挙した本を見て推測できる通りだ。ここでは20歳代の自分が読んでくれると想定して、そんな彼に送る本を列挙したい。いい本との出会いがあることを。
ヤスパース 精神病理学原論 みすず書房
今更、100年前の精神病理学もないだろうと敬遠しないでほしい。患者さんと話をしていて、これは何とカルテに記載すべきなのかという疑問が出てくる。頭に汗して専門用語と格闘して、いったい精神の病気ってどうなってるのだろうと思う。先輩や同僚に聞いたり、教科書を読んだりする。そこで、ヤスパースが教えてくれる。当時の精神医学の潮流がこの本により変わったらしい。その後も精神医学は進歩し、もてはやされる理論や考え方が出ては消えていく。僕たちが信じている精神医学の考え方も、多分歴史は判断を下すだろう。だが客観・主観的なものの関連、「了解」できることとできないこと、人の精神を創り出す基本は、ここにある。
ヤスパースが精神科医として駆け出しの頃、30歳代にこの緻密な理論を創り出したというのだから、天才というのはすごいものだ。
新潮CD 講演 小林秀雄講演(第1巻〜第7巻)
本ではない。茂木健一郎をはじめ多くの人が絶賛している講演のCDだ。これはいい。それに、忙しいきみも合間の時間に聞ける。
小林秀雄は高校生のときから興味があって、何冊か愛蔵している。現在も旅行に行くときは彼の文庫本を持っていき、旅先の夜、読みながら寝るのが僕の習慣だ。そう、彼の本は難しい。だが講演はすごい。プロの落語や漫談の域、といえば誇張しすぎだろうか。すーと聞いても、普通に楽しめる。何度聞いてもそこには発見がある。つまり深いのだ。例えば、第2巻「信ずることと考えること」に出てくる予知夢をみる婦人の話とそれを解釈するベルグソンの話。この話を聞いてどう思うだろうか。きみがぼんやりと感じていた疑問、学会で取り上げられる症例と実際の患者さんとのどこか違う感じ、そのまま記載しようとしてもどうしても抜け落ちてしまう感覚、これが「それだったんだ」と気づかせてくれる。科学者になろうとする人は、彼の科学批判を常にこころに留めておく必要がある。
人格の成熟 A.ストー 同時代ライブラリー92 岩波書店
60年代に書かれた、いわいる力動精神医学を専門とするイギリスの精神医学者が書いた本。一般書店での新書が並ぶ一角は自分にとっていつも楽しい。つい、衝動的に買ってしまい、本棚を超えて何度か古本屋に売ってもまた、新刊が発売され買ってしまう。そんな中から1冊と思ったのが、この本。新書ではなく文庫本だが。
さらっと読むには若干濃い内容だが、こういう本こそ肩を張らずに何となく読むのが楽しかったりする。「一人の子どもが、他人を愛することの出来る一人の大人に成長するまでは、○○を経験した場合でしかない。」本文の結論めいた文章なのだが、○○には何が入るか。答えは「客観的な愛情」なんだそうだ。例えば「自己実現」って言葉が輝いてみえる人、そんな人に関わってる人、「性の問題」を理屈で考えたことのある人にお勧め。