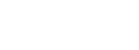教授挨拶

この数年、精神医療を取り巻く環境と、医療自体が大きく変化しています。
第一に我々の社会の抱えるストレス状況はますます厳しくなっており、うつ病、自殺、痴呆老人のQOLと介護、児童青年期の事件などはさまざま問題に直面しています。医学・医療は福祉や教育の領域との連携が求められています。精神医学は治療だけでなく、メンタルヘルス、予防医学として実践的な機能を果たすことが期待されています。
第二に操作的診断基準の登場により、治療法の有効性のエビデンスが世界規模で共有できるようになりました。数年前の治療方針はすっかり新しいものにとって替わられようとしています。これは患者さんにとっては大きな福音です。
第三に脳機能画像の進歩によって精神活動を営んでいるときの脳の活動をボランティアや患者さんで計測できるようになりました。統合失調症、気分障害だけでなく不安障害でも局在的異常活動がPET画像などで分かってきました。たとえば強迫性障害では尾状核での血流異常な増加がみられますが、症状の回復に伴ってこの血流異常も改善することが知られています。長く用いられてきた精神疾患の器質性精神疾患、内因性精神病圏、神経症圏機能の3分類はほとんど意味を失ってしまいました。
このように精神医療は急速に変貌しています。
精神医学的なハンディキャップを持ちながら生きる患者さんに、最新で最高の医療を届けたいと願います。